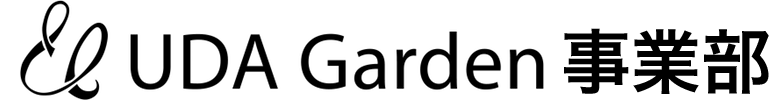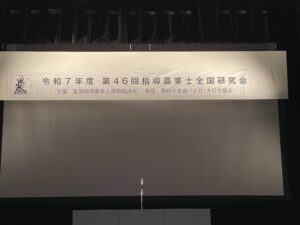『美しい農村と女性の力』レディセミナーに参加して
昨日、公益財団法人 農業振興会館主催の『美アップ農村・レディセミナー』に奈良県農業指導士として参加してきました。
豊かで美しい農業・農村の発展と女性活躍推進をテーマにした勉強会で、農林水産省中国四国農政局 農村振興部長の山田美紀氏による講演は、データに裏打ちされた説得力のある内容でした。
今日は、その講演内容と私自身の考察を交えて書いてみたいと思います。
お米から見える、日本農業の今
女性目線で特に関心を持ったのが、お米の需給状況についてのお話でした。
戦後、食糧不足に苦しんだ日本は、土地改良事業を進めて米の増産に励みました。しかし昭和42年、ついに供給過剰の時代を迎え、昭和46年から減反政策が始まったのです。
それから半世紀以上。
土地改良の成果により天候に左右されにくい安定した生産が可能になり、政策も「面積管理」から「数量目標」へ、さらに平成30年以降は「需要に応じた生産」へと大きく転換してきました。
ところが令和6年産では、思わぬ事態が起きました。
高温による精米歩留まりの悪化。
玄米から精米にする段階で、通常より多くの米が削られてしまうのです。
玄米から精米にする段階で、通常より多くの米が削られてしまうのです。
さらにインバウンド需要の急増、そして意外なことに家庭での米消費量の増加。
これらが重なり、需要見通しが大きく外れ、備蓄米の放出が必要となりました。
この話を聞きながら、私たち花き農家が経験した夏の苦労を思い出していました。
地球温暖化どころか「沸騰化」とも言われる近年の気候変動。
秋から出荷する花壇苗の発芽に、私たちも本当に苦戦させられました。
お米に至っては、収穫後の精米段階でさえも影響が出ているのです。
お米は一年がかりの営みです。農家さんが計画を立て、様々な気候変動や災害に対応しながら、ようやく実らせる大切な作物。
数字で「生産調整」と言われても、すぐに変更できるものではありません。
しかし、現状では、小麦など輸入品の高騰で、国産のお米に注目が集まっていること。
関税がかからず、各家庭で備蓄でき、調理も簡単。
関税がかからず、各家庭で備蓄でき、調理も簡単。
物価高で外食を控える家庭が増える中、お米の価値が大幅に見直されました。
生産者にとっても消費者にとっても納得のいく、安定した価格と食料確保に、国民としては願わずにはいられません。
また、それを支えるために、令和7年3月、土地改良法が一部改正されました。
未来を見据えた土地改良法の改正
改正のポイントは3つです。
施設の保全強化では、戦後整備された農業水利施設の老朽化に対応し、計画的な更新を国や県の発意で進められるようになりました。防災・減災対策では、豪雨の頻度増加を見据えた災害対策の強化。そしてスマート農業対応と多様性の確保では、情報通信基盤の整備
女性の経営参画
第5次男女共同参画基本計画では、理事構成における年齢・性別への配慮と目標数が明記されました。
特に最後の「多様性」という言葉に、私は心を動かされました。
「2人で考える」ことの力
今回のセミナーのメインテーマは、女性活躍の推進でした。
山田部長が紹介された数字には、驚きとともに、もどかしさを感じました。
農業従事者の約4割が女性なのに、認定農業者に占める女性割合はわずか5%。でも、もっと驚いたのはその先のデータです。
女性が経営に参画している経営体の販売金額伸び率は18.3%。参画していない経営体はわずか2%。
この差は何を意味するのでしょうか。
講演の中で特に印象的だったのは、徳島県の「彩(いろどり)」ビジネスを始めた横石さんの言葉でした。
「夫婦は2人で考えて農業をやらなきゃダメだ。1人が考えて、もう1人がそれに従うだけでは、脳みそが1つでやるのと同じ。2人で『ああでもない、こうでもない』と話し合うから、経営は発展していく」
男性が偉いとか、女性はサポートに回るべきだという無意識の思い込み。
それは時代や親、社会の影響によって培われたもので、男性であっても女性であっても、その思い込みが才能や可能性を閉ざしてしまう。この損失の大きさを、私は強く感じました。
見えない壁を乗り越えて
現状の課題は
- 性別による無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)が根強く残存
- 意外だったのは、若い男性に「女性はサポート役」という意識が強い傾向
- 明治民法や戦後の男女別教育の影響が、世代を超えて継承されている
- 家事・育児負担により、女性の活動が制約される
でも、変化も起きています。
とある件のJA女性理事の事例では、女性が入ることで役員会が効率化され、コスト削減が進み、他組織との連携が強化されました。
「役員会でずっと話していた年長男性を誰も止められなかったけれど、女性理事が『そんなこと言ってもしょうがないでしょ』と言って、帰りが早くなった」というエピソードには、笑いとともに頷く参加者が多くいました。
消費者視点や生活者感覚を活かした食育推進、6次産業化の提案。女性ならではの気づきが、新たな価値を生み出しているのです。
これからの目標
男女共同参画基本計画では、令和12年度までに農業委員30%、JA役員20%、土地改良区理事10%の女性登用を目指しています。現在、土地改良区の女性理事割合は全国2.6%(奈良県3%)。まだまだ道のりは長いですが、一歩ずつ前に進んでいます。
私たちにできること
この講演を聞いて、私は改めて思いました。
女性目線と男性目線、双方の見方を上手く取り入れながら、課題を解決し、組織運営を強化していく。それこそが、これからの農業に求められる姿ではないでしょうか。
多様な人材が農業・農村に関わることで、議論は活性化し、新しいアイデアが生まれ、組織は強くなります。
特に女性の効率化能力や他組織との連携力は、持続可能な農業経営に不可欠です。
性別による思い込みを解消し、真の意味での男女共同参画を実現すること。
それは、日本農業の未来を明るくする、大切な一歩なのではないでしょうか。